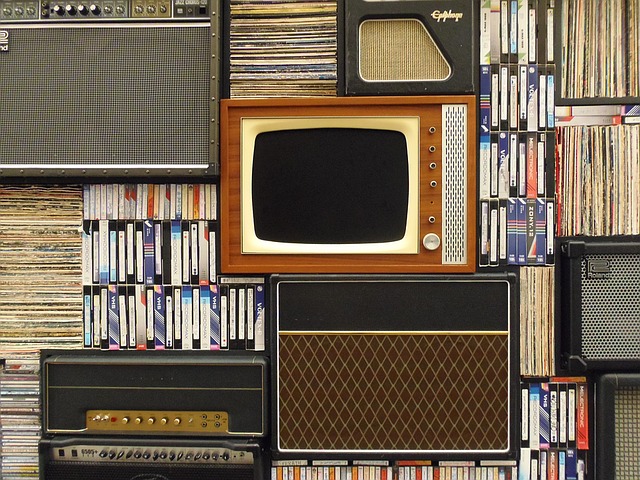オリジナルエピソードの中で印象に残ったものについてふれてみます。
オリジナルエピソードから
ミスタービーンのテディ
テディ(Teddy)は、ミスタービーンが所有する小さな茶色のテディベアです。イギリスやその他の国々では、クマのぬいぐるみのことを「テディ」と呼ぶことがあります。テディはシンプルなクマのデザインで、黒いビーズのような目と縫い付けられた鼻がついています。
テディは、ミスタービーンの最愛の「友達」であり相棒です。ビーンはテディを単なるぬいぐるみとしてではなく、まるで生きているかのように扱い、話しかけたり、一緒に行動したりします。旅行に連れて行ったり、寝るときにはベッドに連れて行ったり、テディに「叱る」ふりをしたり、助手席に乗せて一緒にドライブしたり、寝かしつけたり、面倒を見たりします。
クリスマスには、テディはミスタービーンからボタンの目をもらいます。目をつけたことで、テディは初めて世の中が見えるようになったようで、ミスタービーンは「ハロー、そう、僕がビーンだよ」といった仕草を見せます。テディは視力が悪いのか、時おり針金の眼鏡をかけていることもあります。
ホリデーで「426号室」に宿泊したとき、ミスタービーンはテディをベッドサイドテーブルの引き出しに寝かせます。しかし、勢いよく引き出しを閉めたのでテディの首がもげてしまいます。また、ホリデーの準備のために荷物を容なく減らすモードに入っているミスタービーンは、テディも小さくできないか考えてしまいます。足を切るか頭を切るか悩みます。「Ohhh」という「かわいそうじゃないの」という視聴者の声が背景から聞こえてきます。
また、コインランドリーでテディを洗い乾燥機で回されたテディは小さくなってしまったり、ミスタービーンが自分の部屋をDIYしているシーンでは、刷毛が見つからず、テディを使ってペンキを塗る場面も。映画版でのテディは、体のサイズに比べて頭が小さいように見えます。
ロンドンの観光地では、テディのぬいぐるみがよく販売されているのを見かけます。
悲しい年末のパーティ
ミスタービーンは自分の部屋で大晦日のパーティを開きます。パーティーには、珍しく友人が2人訪れました。
ミスタービーンが全員のために作っておいたパーティハットは新聞紙を折ったもの笑。彼は、ドリンクとスナックを用意するためキッチンに行きます。スナック用の「Twiglets」の缶を開け、1つ食べ「美味しい」と満足するミスタービーン。でも、残りはたった1つ。そこで、ミスタービーンは窓から手を伸ばして木の枝を切り、それにマーマイトをつけて皿に並べます。
「Twiglets」はイギリスで長年人気のある小麦ベースのスナックで、「枝(twig)」のようなゴツゴツした形状と、酵母エキスによる独特の塩辛い味が特徴です。チーズ味もあります。そのため、ミスタービーンは枝にマーマイト(酵母エキスで作られている)をつけているわけです。ちなみに、マーマイトはビールを作る過程でできる副産物です。
私はマーマイトが好きですが「Twiglet」はあまり好みではありません。マーマイトはイギリス人でも好き嫌いが分かれます。マーマイトは熱々のトーストにバターを塗って、マーマイトを極々薄く塗るのが美味しく食べるコツです。コンソメのような風味でもあるので、私は隠し味的に使うこともあります。「Twiglets」は香りが独特なので、昔、帰宅したとき、部屋の中の匂いで、家族が「Twiglets」のチーズ味を食べていたことがすぐにわかったことがあります。
また、ワインがないため、ミスタービーンは酢で代用します。酢を飲んだときのビーンのリアクションが秀逸です。そして彼は、最後の「Twiglets」1本と木の枝を皿に並べ、自分だけ本物を食べてしまいます。結局、彼はパーティハットしか用意していなかったのか笑。
友人たちは奇妙な大晦日のパーティから早く退散するために時計の針を進めてしまいます。年が明けたと思ったミスタービーンは、友人2人とテディを入れた4人で(笑)輪になるように手をつなぎ、「蛍の光」を歌います。イギリスでは「蛍の光」(Auld Lang Syne、スコットランド民謡)を輪になって歌うのが新年の伝統として知られています。日本のように卒業式では一般的に歌われません。
時計が進んでいるので、ミスタービーンは他の部屋から聞こえてくる「A Happy New Year!」という歓声をベッドの中で聞くことになるのです。
セールとDIY
ミスタービーンは「1月のセール(January Sale)」に行き、ソファやDIYの道具を買い込みます。そして、部屋の模様替えを始めます。
日本でもDIYの人気がだいぶ広まってますね。イギリスでは修理や何かを作ったりすることは、多くの家庭で行われます。私も、カーテンを替えるといった簡単な作業だけでなく、カーテンレールの取り替え、ブラインドの設置、壁や庭のフェンスのペンキ塗り、オーブンや換気扇の取り替え、カーペットの交換、風呂場のタイル貼りと目地作業、水回りのシーラント、ドアの隙間風対策、鍵の交換、家具の修復、棚の作成、ソーイングなど、さまざまなDIYをしたことがあります。
ミスタービーンは部屋の壁を白く塗りたかったようで、あるものを使って一気に作業を進めることにします。出来上がりは真っ白になり、ちょっとしたサプライズがありますが、あんな真っ白でよかったのかと疑問に思ってしまいました笑。
衛兵とカメラ
ミスタービーンは、衛兵(Queen’s Guard)と一緒に写真撮影を試みます。衛兵が基本的に動かないよう厳しく訓練されていることをいいことに、衛兵の制服の埃を払ったり、ボタンを磨いたり、熊皮帽(bearskin)や口ひげを整えたり、花を飾ったり、テディを銃剣に引っかけたりして、衛兵をデコレーションします。
衛兵は「衛兵の任務(Guard Mounting)」中、定められた位置で直立不動の姿勢を保つことが求められ、観光客の行動や天候などの外部からの刺激にも反応しないように指導されています。ただし、交代のときには当然ながら動きますし、観光客が過度に接近したり危険な行動を取った場合には、警告のために声を発したり行動をとることもあります。特に、ふざけて衛兵にちょっかいを出す観光客は、場合によっては取り押さえられることもあるようです。衛兵は厳しい訓練を受けた職務中の軍人であるため、無礼な振る舞いをすると深刻な結果を招くおそれがあるということですね。衛兵はバッキンガム宮殿の他に、ロンドン塔、ホース・ガーズ(近衛騎兵隊本部)、ウィンザー城などに配置されています。
おわりに
シットコムにはよく笑い声が挿入されていますが、それだけでなく、観客の驚きの声や同情の声なども含まれています。
たとえば、ミスタービーンが旅行の準備でテディの首を切ろうとしたときや、愛車のミニクーパーが憂き目に遭ったときには、「Ohhh」という同情の声が流れます。また、ミスタービーンがオープンデー(公開授業)でズボンを取られてしまい、それを追跡して取り返した場面では大きな拍手が起こりました。特に同情の「Ohhh」が起こると、私もつい一緒になって同情してしまいます笑。